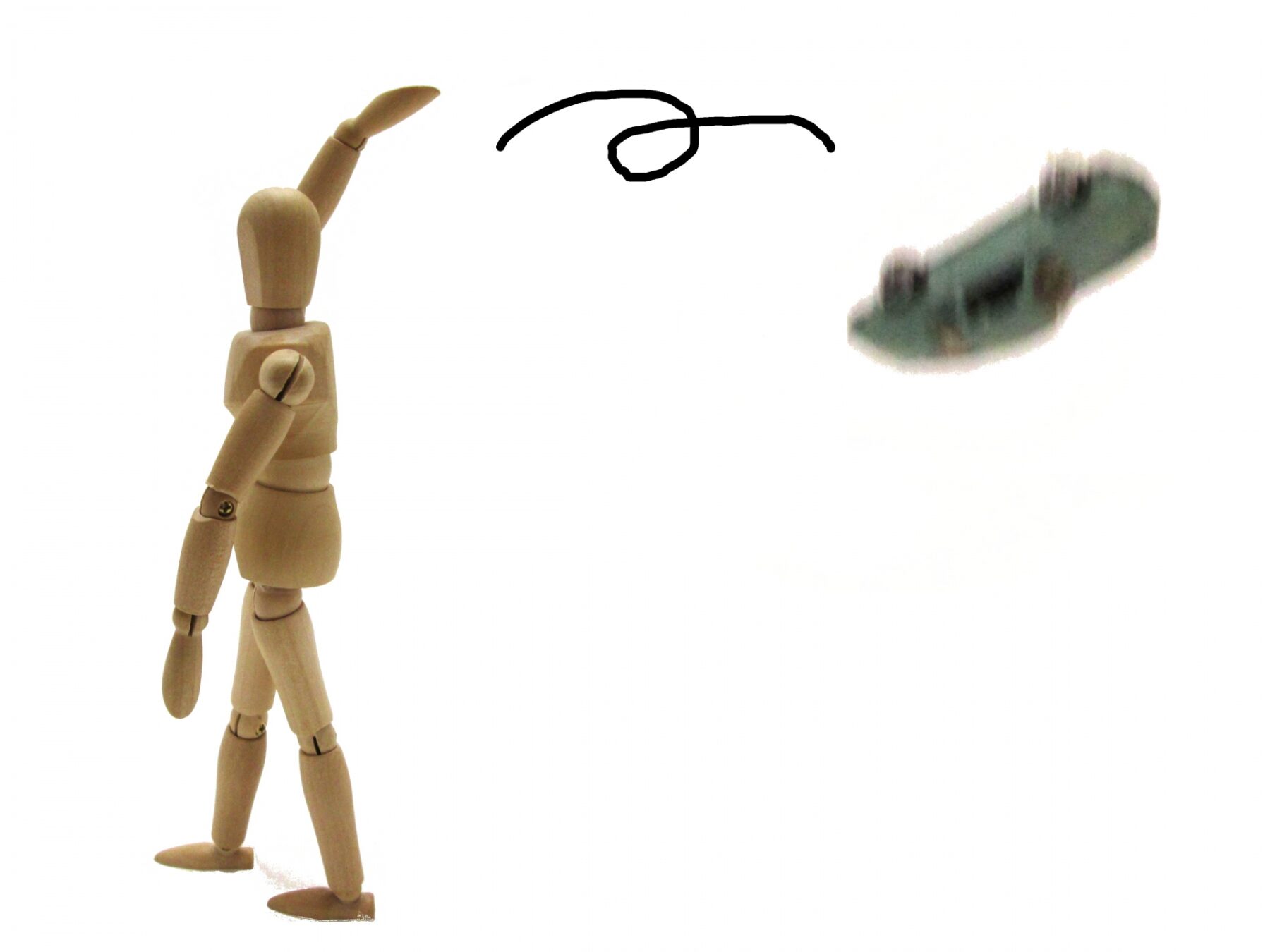車が13年目を迎えると、自動車税の増税や車検での修理費用の増加など、維持にかかる負担が大きくなります。
そのため「このまま乗り続けるべきか」「乗り換えたほうがいいのか」と悩む方が増えます。
この記事では、13年落ちの車にまつわる税金や車検のポイント、修理費用や下取り価格、さらには乗り続ける人の特徴や最適な乗り換えタイミングについて詳しく解説します。
あなたの賢いカーライフの判断材料にお役立てください。
記事のポイント
13年目で自動車税と重量税が増加し維持費が上昇
車検時に劣化部品の予防整備で修理費用が高額になる傾向
13年落ち車は市場価値が下がり、下取り価格も低くなる現実
乗り換えは車検時や大きな修理見積もりが出た際が適切なタイミング
車の状態が良好なら定期整備で13年目以降も乗り続ける選択肢も有効
車が13年目だけど乗り続ける方がいい?

13年という節目を迎えた愛車を前に、「乗り続けるべきか、乗り換えるべきか」という問いについて、税金、メンテナンス、資産価値、そして乗り続ける魅力まで、様々な角度から掘り下げることが重要です。
車の登録から13年経つとどうなる?
新車登録から13年経過した車は、税金面と維持費の面で変化が起こるため、乗り続けるかどうか慎重な判断が必要です。
まず、13年目を越えると自動車税や自動車重量税が引き上げられます。
これにより、毎年の維持コストが増加します。
毎年5月頃に納める自動車税は、13年目を境に約15%(ディーゼル車は11年目から約15%)高くなります。
例えば、排気量1.5L超~2.0L以下の一般的な乗用車(年間39,500円)であれば、約45,400円となり、年間約6,000円の負担増です。
これは乗り続ける限り、毎年続くコストとなります。
また、経年による車体の劣化も影響し、車検時の修理・交換部品が増えて修理代が高くなる場合があります。
タイヤやエンジン部品、ゴム製のパーツの摩耗や劣化が進みやすく、車検での整備費用がかさむことが一般的です。
さらに、13年を超えると車の市場価値も大きく下がる傾向にあります。
状態が良好なクラシックカーなどを除き、一般的な車の場合は買い替え時期として見なされることが多いです。
しかし、車の状態が良好であれば、適切なメンテナンスを行いながら乗り続ける選択肢もあります。
定期的な点検・整備を欠かさず実施することで、安全性や車のコンディションを維持することは可能です。
車が13年目の車検はどうなる?

愛車との付き合いが13年目を迎え、5回目あるいは6回目の車検がやってきます。
これまでの車検と何が違うのか、費用はどれくらい見ておけばいいのか。
費用面と整備面、2つの観点からその実態に迫ります。
- 費用面:避けて通れない法定費用の増加
まず、誰にでも必ず影響するのが法定費用の値上がりです。
自動車重量税の重課が、車検費用を直接押し上げます。 - 整備面:予防整備が必須となるステージへ
13年目の車検で最も重要かつ費用を左右するのが、この整備内容です。
これまでは「壊れたら直す」「劣化したら交換する」という対症療法的な整備で済んでいたかもしれません。
しかし、この年式になると「壊れる前に交換する」という『予防整備』の視点が不可欠になります。
特に以下のパーツは、このタイミングでの点検・交換を推奨したい代表格です。
- 足回りのゴム部品(ブーツ類、ブッシュ類)
ドライブシャフトブーツやステアリングラックブーツなどが破れていると車検に通りません。
硬化してひび割れたブッシュは、乗り心地の悪化や異音の原因になります。
目に見えない部分ですが、安全な走りを支える重要なパーツです。 - 冷却系統(ウォーターポンプ、ラジエーターホース)
エンジンの冷却を担う心臓部です。
ウォーターポンプからの水漏れや、ホースの硬化による亀裂は、オーバーヒートに繋がります。
予防的に交換しておくことで、安心して運転に集中できます。 - ブレーキ系統(ブレーキホース、キャリパー)
ブレーキフルードは2年ごとの交換が基本ですが、その圧力を伝えるブレーキホースもゴム製です。
13年も経てば劣化は避けられません。
ブレーキの効きを左右するキャリパーの固着なども起きやすくなるため、分解しての点検(オーバーホール)も視野に入れるべきでしょう。
これらの部品交換が重なると、整備費用だけで10万円、場合によっては20万円を超えることもあります。
13年落ちの車を買うときの注意点は?

車の外観や内装、エンジンの状態を、しっかりチェックすることが必須です。
実際に現物を見て、試乗を行い、走行中の異音や振動の有無も確認しましょう。
特にエンジン音やマフラーの異音、タイヤの摩耗具合、ブレーキの効き具合は重要なポイントです。
また、冠水車や修復歴がある場合は慎重に判断しましょう。
また、走行距離と年式のバランスにも注意が必要です。
年式に比べて走行距離が極端に少ない場合は、長期間放置されていた可能性もあります。
逆に距離が多すぎる場合は、主要部品の摩耗が進んでいる場合があります。
次に、13年落ちということで税金や維持費の負担が増える点を理解しておくことも重要です。
13年を超えると自動車税が高くなり、車検ごとの重量税も増額されるため、月々の維持コストが変わる可能性があります。
最後に、購入前にメンテナンス履歴の確認を徹底することが、長く安心して乗る上で欠かせません。
定期的にオイル交換や消耗部品の交換がされているか、整備記録が残っているかをチェックしましょう。
これにより、購入後の突発的な故障や修理リスクを減らすことができます。
車を長く乗る人の性格は?
車を13年以上愛用し続ける人には、いくつか共通する性格や価値観があります。
- モノへの愛着と物語を大切にする
車を単なる移動の道具としてではなく、苦楽を共にしてきた相棒として捉えている。
これが、長く乗り続ける人の最も根源的な特徴でしょう。
彼らにとって車は、家族との旅行の思い出、若い頃に友人と無茶をした記憶、雨の日に一人で聴いた音楽など、数えきれないほどの物語が詰まったタイムカプセルのような存在です。
ボディについた小さな傷ひとつにもストーリーがあり、それを味として受け入れています。
最新の機能や燃費性能よりも、これまで積み重ねてきた時間と経験にこそ価値を見出す一面を持っています。
- 合理的で本質を見抜く現実主義
彼らは「車を買い替える」という行為に伴う、目に見えないコストを熟知しています。新しい車を選ぶための時間、ディーラーとの交渉、各種手続きの手間、そして何より、新車が納車された瞬間から始まる急激な価値の下落。
それらを天秤にかけた時、「今の愛車をきちんとメンテナンスして乗り続ける方が、総合的に見て経済的で合理的だ」と判断するのです。
流行りや見栄に惑わされず、自分にとっての本当のコストパフォーマンスは何かを理解している。
そんなスマートな現実主義者でもあります。
- 変化を恐れず、むしろ楽しむことができる
「古い車は故障が心配…」というのは一般的な感覚です。
しかし、長く乗る人は、その不便さや予測不能性すらも、カーライフのスパイスとして楽しむ術を知っています。
例えば、少し調子が悪くなれば、「お、今回はどこがご機嫌斜めかな?」と、愛車の発するサインに耳を傾け、原因を探ることを面白がります。
信頼できる整備士と「ああでもない、こうでもない」と対策を練る時間を、コミュニケーションの機会として楽しむ。
自分でできる範囲のメンテナンスに挑戦し、車の構造を学ぶことに喜びを見出す。
完璧ではないからこそ、手がかかる。
そして、手がかかるからこそ、愛着が深まる。
この好循環を自ら作り出せる人こそ、一台の車と長く付き合える資質の持ち主なのです。
このように、車を長く乗り続ける人たちは、モノを大切にする心、冷静な判断力、そして変化を楽しむ遊び心を兼ね備えた、実に魅力的な人々といえるでしょう。
車が13年目だけど乗り続ける方がいい?│乗り換えのタイミング

13年目の車に乗り続けるべきかは、多くの要素を考慮した総合的な決断が必要です。
維持費用、車の状態、市場価値、安全性、そして個人的なライフスタイルの変化をよく見極めることが大切です。
劣化に伴う高額な修理費用の発生
13年という歳月は、車の心臓部や神経系統といった基幹部品が、次々と寿命を迎えるフェーズに突入します。
CASE 1:発電・燃料系統のトラブル
13年落ちの車で発生する、主なトラブルの原因がこれらです。
- オルタネーター(発電機)の故障:修理費用 5万円~15万円
バッテリーに電気を供給する、まさに車の発電所。
これが壊れるとバッテリーの電力を使い果たすまでしか走れず、やがて警告灯が点灯し、オーディオが消えエンジンも停止します。
リビルト品(再生部品)を使っても、工賃を含めればこの程度の出費は覚悟すべきです。 - 燃料ポンプの故障:修理費用 5万円~10万円
ガソリンをエンジンに送り込むポンプです。
寿命が近づくと異音が出たり、エンジンのかかりが悪くなったりしますが、多くの場合、何の前触れもなく突然停止します。
CASE 2:エアコン系統のトラブル
真夏の渋滞、窓を閉め切った車内でエアコンが突然ただの送風機に…。
これもまた、13年モノが直面する悪夢の一つです。
- エアコンコンプレッサーの故障:修理費用 10万円~20万円
冷媒ガスを圧縮する心臓部が、コンプレッサーです。
内部の焼き付きやガス漏れが起きやすく、交換には高額な費用がかかります。
さらに、関連する部品も同時交換というパターンが多いです。
CASE 3:駆動・操舵系統のトラブル
オーナーにとって最も経済的ダメージが大きいのが、動力伝達を担うトランスミッションの故障です。
- トランスミッション(AT/CVT)の故障:修理費用 20万円~50万円以上
変速時に大きなショックがある、特定のギアに入らない、滑るような感覚があるといった症状が出たら危険信号です。
内部のバルブボディやクラッチの異常が考えられ、修理はミッション本体の載せ替え(交換)となるケースがほとんど。
この修理費用が、多くのオーナーが愛車を手放す直接的な引き金となっています。
乗り続けるという選択は、こうした不意の出費に備え、常に数十万円単位の修理用貯金を確保しておく覚悟が求められます。
年式が古いことによる下取り価格の低下
中古車査定の世界には、古くから「10年10万km」という、価値が大きく下落する一つの目安が存在します。
そして13年という年式は、その壁をさらに超えた先にあります。
価値が低くなる理由
- 再販の難しさ
買取店やディーラーは、下取った車を中古車として再販することで利益を得ます。
しかし13年落ちの車は、前述したような故障リスクの高さから、買い手を見つけるのが非常に困難です。
また、販売後の保証を付けることも難しく、商品として極めて扱いにくいのです。 - 海外への販路減少
かつて日本の年式の古い中古車は、耐久性の高さから海外、特に新興国で絶大な人気を誇りました。
しかし近年は、各国の輸入規制強化(年式制限など)により、10年以上前の車を輸出できる国が減少しています。
販路が狭まれば、当然ながら買取価格も下がります。 - 部品取りとしての価値低下
再販も輸出も難しい車に残された道は、部品取り車として解体されることです。
しかし、これも需要があってこそ。あまりに古いモデルだと部品の需要自体がなく、最終的には鉄資源としてリサイクルされるしかありません。
これらの要因が重なり、13年落ちの車の査定額は、多くの場合低評価になってしまうのが現実です。
価値が残る例外的なモデル
もちろん、すべての13年落ちの車が無価値というわけではありません。
- 国産スポーツカー(GT-R、スープラ、シビックタイプRなど)
JDM(日本製スポーツカー)ブームにより、海外からの需要が異常なほど高騰しています。 - 一部のSUV(ランドクルーザー、ジムニーなど)
悪路走破性と耐久性が世界的に評価され、年式を問わず高い人気を誇ります。 - 希少な限定車や特殊グレード
生産台数が少なく、マニアからの需要が高いモデル。
これらの車は、13年落ちであっても驚くような高値で取引されることがあります。
しかし、これらはあくまで例外中の例外。
一般的なファミリーカーやコンパクトカー、セダンにおいて、高いリセールバリューを期待するのは難しいです。

乗り換えを検討する最適なタイミングは?

乗り換えを真剣に検討すべき「3つの潮時」を具体的にお伝えします。
これは、あなたの愛車人生における、最も重要な判断の羅針盤となるはずです。
タイミング 1:次回の車検が見えてきた時
これは最も分かりやすく、かつ合理的な判断が下せるタイミングです。
車検満了日の3〜4ヶ月前になったら、一度立ち止まって冷静にシミュレーションしてみましょう。
【天秤にかけるべきもの】
(A)乗り続けるコスト
今回の車検で支払うであろう法定費用(重課された重量税を含む)+整備費用の見積もり額。
それに加え、次の2年間で発生しうる自動車税(重課分)+突発的な修理費用の備え(最低でも10万~20万円)を足し合わせます。
(B)乗り換えるコスト
新しい車(新車・中古車問わず)の頭金や初期費用。
この(A)と(B)を比較してみてください。
もし(A)の金額が(B)に匹敵する、あるいはそれを超えるようなら、それは乗り換えのサインです。
「あと2年乗るために数十万円を投じる価値があるのか?」と自問してみてください。
車検を通してしまった直後に高額な故障が発生するのが、経済的にも精神的にも最もダメージが大きいパターンです。
タイミング 2:10万円以上の修理見積もりが出された時
オルタネーター、エアコン、オートマチックトランスミッション…。
ある日突然、整備工場から告げられる10万円超えの見積もり。
これが、潮時と考えるタイミングです。
感情的に「これまで長く乗ってきたんだから、直してあげたい」と思うかもしれません。
しかし、その10万円、20万円を次の車の頭金にすれば、より安全で、快適で、燃費の良い未来を手に入れるための資金になります。
一つの大きな故障は、他の部品も同じように限界が近いことを示す警告灯です。
傷口が浅いうちに決断することが、結果的にあなたの資産を守ることにつながります。
タイミング 3:ライフスタイルが変化した時
車は、人生を映す鏡です。
家族構成、仕事、住む場所、趣味。
ライフスタイルの変化が、買い替えのタイミングと考えます。
- 子供が独立し、大きなミニバンは不要になった。
- 通勤で毎日乗るようになり、最新の安全運転支援システムが欲しくなった。
- 週末のアウトドアに目覚め、悪路に強いSUVに興味が湧いた。
- 高齢の親を乗せる機会が増え、乗り降りのしやすいスライドドアの車が必要になった。
これらのタイミングは、次の新しいステージへと進むための出発の合図なのかもしれません。
車の状態が良好であれば乗り続けることも
13年目の車でも、状態が良好であれば乗り続けるのは十分に現実的な選択肢です。
年数が経っていても、定期的なメンテナンスや適切なケアを受けている車は、信頼性が高く、快適な走行を提供してくれます。
まず、メカニカルな部分がしっかりと機能していることが確認できれば、それは大きな安心材料です。
エンジンやトランスミッションに問題がなく、ブレーキやサスペンションも状態が良いのであれば、安全性も確保されています。
さらに、外観や内装がきれいに保たれていれば、愛着を持って乗り続けることもできます。
特に、思い出が詰まった車であれば、その価値は単なる市場価値以上のものとなります。
経済的な側面でも、車の状態が良ければ、すぐに新車を買う必要はありません。
新しい車の購入は大きな投資です。
現在乗っている車の維持費や燃費が納得できる範囲であれば、そのまま乗り続けることで費用を節約できるでしょう。
信頼できるメカニックに定期的にチェックしてもらい、問題がある部分がないか注意を払うことが大切です。
総括│車が13年目だけど乗り続ける方がいい?
車が13年目を迎えると、自動車税や重量税の増税、そして経年劣化による修理費の増加という維持費のダブルパンチが始まります。
これにより、車検費用やメンテナンスコストが大幅に上昇し、税金負担も増えるため、経済的な負担が重くなるのが現実です。
また、市場では年式が古い車の価値が下がりやすく、下取りや売却価格も低くなる傾向にあります。
これに伴い、故障リスクや修理費用の増加と合わせて考えると、13年目の車検を機に乗り換えを検討するのが合理的な判断です。
一方で、走行距離が少なく、定期的にメンテナンスをしっかり受けているなど車の状態が良好であれば、乗り続ける選択肢も十分にあります。